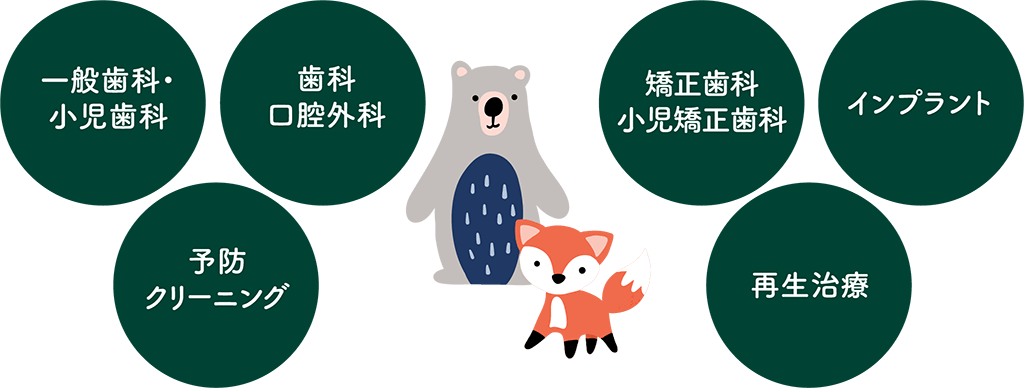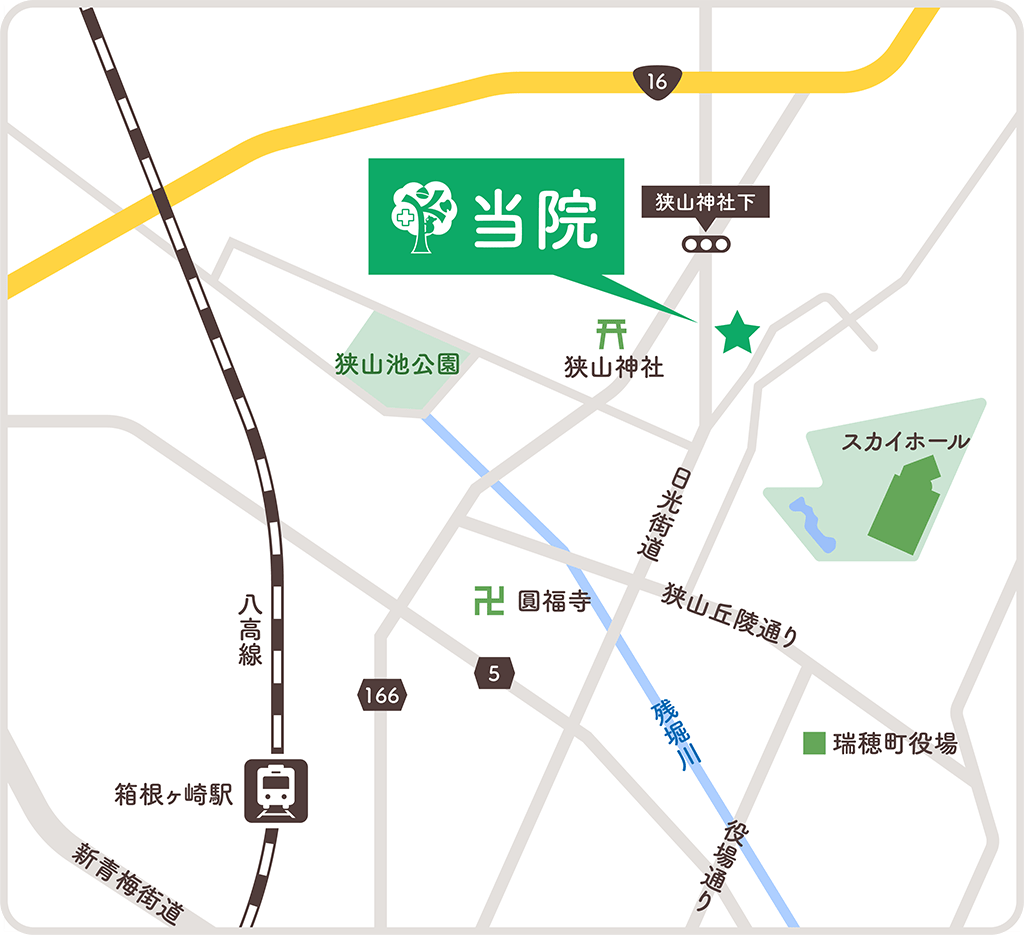西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎で歯科・歯医者をお探しの方は栗原医科歯科医院・矯正歯科まで
CONCEPTお口から全身まで
皆さまの健康を末永く
当院は内科と歯科が一緒になった、小さなお子さまから
大人の方まで安心して通える総合診療所です。
80年近く続く内科診療と、大学病院で歯周病治療・矯正治療を専門的に診療してきた2人の歯科医師による、
大学病院レベルの歯科治療・予防治療・矯正治療で
地域の皆さまの健康をサポートしてまいります。

体の元気と健康な
口腔環境のサポートで
地域のみんなを
応援しているよ!
口腔環境のサポートで
地域のみんなを
応援しているよ!
ご予約・
お問い合わせ042-557-0100
お問い合わせ042-557-0100
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |
| 15:00-18:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ▲ | ー | ー |
▲:13:00~15:00 休診日:水曜・日曜・祝日
NEWS
-
- 2024.02.06
- 休日診療のお知らせ
医科のみ2月23日(金)9時~12時、13時~15時休日診療いたします。
-
- 2023.12.25
- ホームページ公開いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
ご予約・
お問い合わせ042-557-8877
お問い合わせ042-557-8877
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30-18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ★ | ー | ー |
★:14:30〜18:00 休診日:水曜・日曜・祝日
最終受付:30分前まで
NEWS
-
- 2024.03.15
- 休診のお知らせ
3月29日(金) 栗原ひかる先生 府中けやき通り矯正歯科にて勤務のため休診となります。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いします。
-
- 2023.12.25
- ホームページ公開いたしました今後ともよろしくお願いいたします。
駐車場22台完備で
アクセス良好!
アクセス良好!
ACCESSアクセス
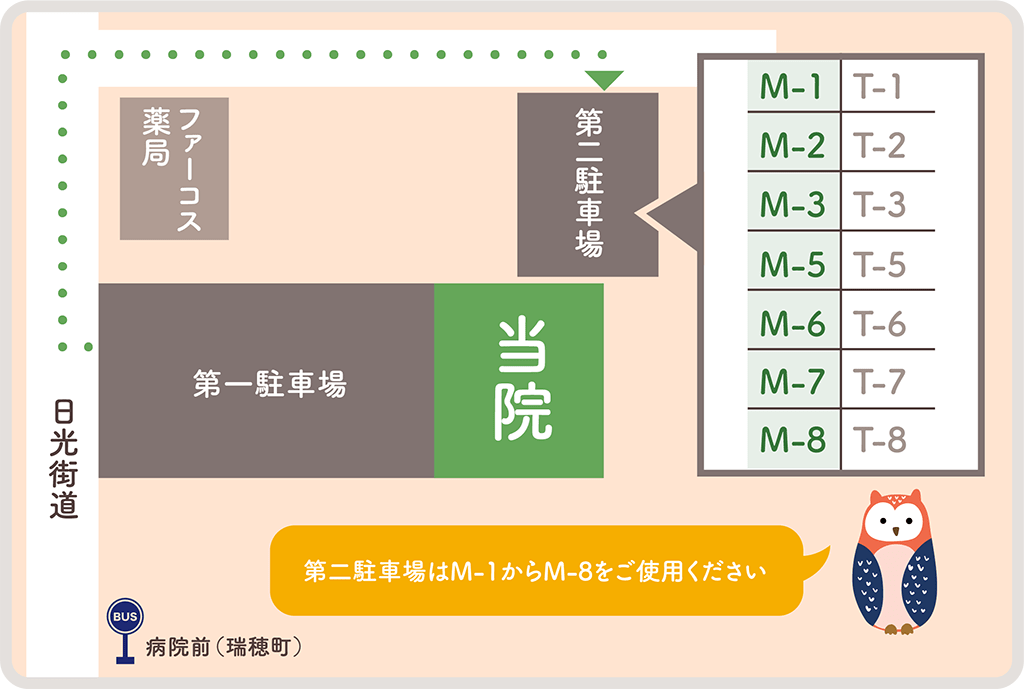
-
お車でお越しの方
医院前に15台分、
第二駐車場に7台分の駐車スペースを設けています。 -
電車でお越しの方
JR八高線
【箱根ケ崎駅】から徒歩12分 -
バスでお越しの方
西武バス入間市駅行
【病院前バス停】目の前